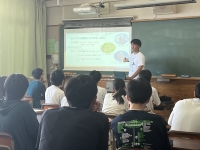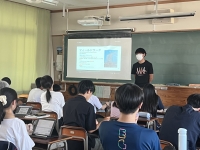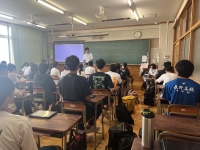3年選択生の課題研究発表会を実施
2025年07月16日
2年生を聴衆に、これまで取り組んできた研究の成果を発表しました
3年生の総合の時間「グローカルアカデミア」は、選択生の授業です。7月14日(月)が最後の授業で、2年生を聴衆に課題研究発表会を行いました。
発表会は、2年生の各教室に3人ずつが入って、ひとり12分間の持ち時間でプレゼンテーションと質疑応答を行いました。2年次から継続している研究も、3年生になってフィールドワークや実験、調査などを追加して内容をブラッシュアップさせたり、新たにテーマを設定して始めた課題研究など、それぞれに熱意のある発表でした。
以下は、3年生の発表タイトルです。(名簿順)
1組 岡田さん「サブサハラ・アフリカにおける学歴社会~発展の鍵か障壁か~」
1組 目次さん「牛とヒトがよりよい形で共存するために」
1組 ブリザードさん「教科書を学ぶ。教科書で学ぶ。」
2組 岩井さん「森将軍塚古墳に生息する野鳥と環境との関係」
3組 権田さん「”行ってみたい”を”行けた”に変える」
3組 寺沢さん「千曲市を洪水から救うには?」
3組 宮下さん「商店街の魅力とこれから in 権堂商店街」
3組 義家さん「和菓子を世界で流行させることはできるのか?」
3組 渡邊さん「脳オルガノイドの研究は社会にどのような議論をもたらすべきか?」
4組 渥美さん「廃棄物から生まれるオーガニックコスメ素材の探究」
4組 伊藤さん「少子化社会の義務教育」
4組 岩佐さん「図書館で地域経済を活性化させるには」
4組 檀原さん「これからの日本の報道はどうあるべきか」
5組 橘田さん「地域創生と住民の関わりについて」
5組 豊田さん「平等とは何だろう?~特別編~」
5組 西岡さん「花粉で溢れる春を穏やかにしよう」
6組 傳田さん「災害時の薬剤師の役割」
7組 鈴木さん「洗剤をつくる」
7組 深美さん「昭和レトロリバイバル~なぜ人は懐かしさを求めるのか~」
今年度は、例年以上に大勢の3年生がグローカルアカデミアを選択してくれました。先月行われた上田高校主催の「令和7年度 北陸新幹線サミット」に参加した生徒は、県内外で同じように課題研究に取り組んでいる同世代と積極的に意見を交換し合いました。発表の場の直前までフィールドワーク先を模索する生徒や、1・2年生に向けた海外挑戦のための説明会を企画する生徒たちもいました。また、特別非常勤講師の、東京大学の佐野先生が来校された時には意欲的に質問や相談をする生徒が多かったことも印象的でした。
3年生のグローカルアカデミアは、発表会でひと区切りです。授業は終わりますが、今後は、活動成果を残す研究集録の発行に向けて、各自で論文をまとめることになっています。自分たちの探究心を高校での活動にとどめることなく、ぜひ大学以降の学びに繋げていってください。
発表を聞いた2年生の感想などの抜粋です。夏休みに向けて本格的に研究活動を進めている2年生にとって参考になるところが多かったことと思います。
・問題提起から調査・実験、考察、結論までの流れが明確で、聞いていて理解しやすのかったので、自分も内容だけでなく、どう伝えるか、どう考察を深めるかを意識して取り組んでいきたいです。
・どんなに些細なことでも疑問をひとつずつ解決している姿勢が印象的でした。自分の仮説や疑問を深めていくことを大切にしたいです。
・自分が想像している以上にフィールドワークでの学びは大きいし、文献調査のデータには説得力があると感じた。
・実験をしたり、FWやシンポジウムに行ったりするなど色々な研究方法があったから、自分の研究テーマに合った研究方法を試しいていきたい。研究の進め方など、とても参考になった。
・全員共通していたのが、FWだけで研究が終わるのではなくわかったことからさらに知りたいことを追究するという姿勢だった。追究していく研究を進めたい。
今年度の発表会は、信州大学の教職員大学院の先生方に参観していただきました。各教室で生徒たちの発表に対する講評や、探究活動へ感想などもいただきました。先生方、お忙しい中、ありがとうございました。
・高校生が自分の興味のある分野をとことん追究し、成果を発表する経験は、大学に進んでからも役に立ってくると思いました。私が高校生の時は総合的な学習が行われておらず、何かを追究することなく大学生になってしまった。高校生には、このような貴重な経験を大切にして欲しい。
・それぞれが探究の時間に意欲をもっている熱量を感じました。調べたい、なんとかしたいという思いがあるからこそ考えられているのだなと思いました。発表もわかりやすくまとめられている印象でした。具体的な行動に移していけるのと、そこからの分析の過程がわかりやすく、探究活動の意義を感じました。
・単純に思った点としては、学術的な研究の活用の程度についてです。それぞれの発表者のテーマの決定理由は、自分の生活や経験に基づいたものが多く、テーマへの想いは十分に伝わってきました。しかしながら、学術的な研究や関連する資料を用いて発表を行うという姿は中々見られませんでした。自分のテーマについて関連する資料や学術研究を1つか2つでもいいので見ることは重要だと考えます。学術研究を読むことで問の立て方やその分野の研究の方向性を知ることができるからです。そこを知らないと、テーマは良くてもその問題、テーマに対する視点の質が悪く、無駄な研究に終わってしまう可能性があるため、もう少し学術的な研究の面が促進されていくとより良い探求になるのではないかと感じました。